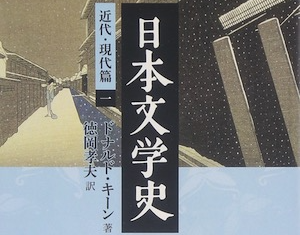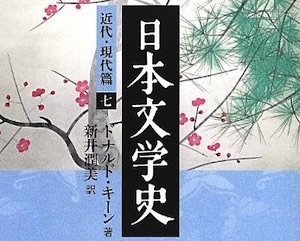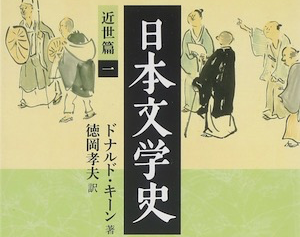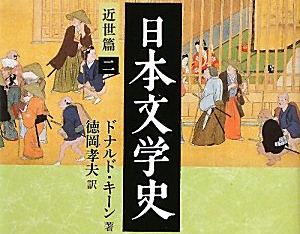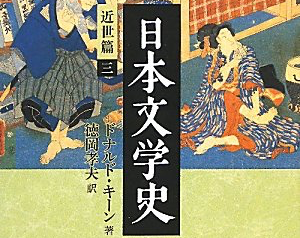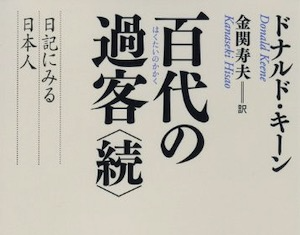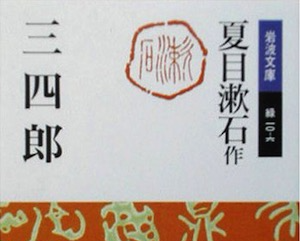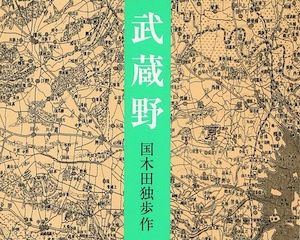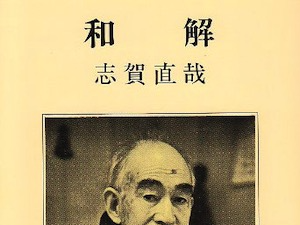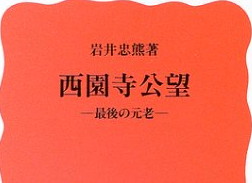日本文学史 近代・現代篇〈二〉
ドナルド・キーン著、徳岡孝夫訳
中公文庫
特定の作家への思い入れが伝わってくる

ドナルド・キーンの畢生の大作、『日本文学史』の第五巻は、『日本文学史 近代・現代篇〈一〉』の続きで、「近代・現代篇〈二〉」である。本書で扱われているのは、自然主義、夏目漱石、森鴎外、白樺派で、それぞれが一つの章に割り当てられ、章立てされている。
「自然主義」の章では、フランスの自然主義が日本では私小説的な方向に偏向していって、世界的な自然主義と別の方向に進んでいった過程が描かれる。取り上げられる作家は、国木田独歩、田山花袋、島崎藤村、徳田秋声、正宗白鳥、近松秋江、岩野泡鳴で、独歩が自然主義に入っているのは違和感がある(浪漫主義の方が近いような気がする)が、島崎藤村が独歩を自然主義作家と位置付けていたことから、日本では自然主義の流れの中で扱われるらしい。作家ごとにそれぞれの著作が紹介されるというアプローチはこれまでと同じで、いかにも「文学通史」風だが、田山花袋の『蒲団』のスキャンダルも詳細に紹介されており、当時の時代背景がよくわかるようになっている。この項だけでも十分読む価値がある充実した章に仕上がっている。
それに続く夏目漱石、森鴎外の章は、この二人が一般的に個々に論じられることが多い作家であることもあり、それほど目を引くような要素はなかった。もちろん文学史として考えれば重要な項であり、「文学史」の中で必要性が高いことは言うまでもない。個人的には、本書からは、漱石より鴎外の解説の方に学ぶものが多かったが、これは僕自身が森鴎外のことをあまり好きではなく、よく知らなかったためである。『百代の過客〈続〉』を読むと、著者自身も鴎外の方に多大な関心を持っているようだ。このような(特定作家への思い入れの)傾向は、先ほどの自然主義作家にも当てはまり、特に国木田独歩、徳田秋声への関心の高さが『百代の過客〈続〉』からは窺われたが、その姿勢は本書でも反映されている。このように、各作家ごとに著者の温度差が若干あるようで、したがって読者の方も、著者の温度が高い作家の方に関心が向けられることになる。もちろん、それはそれで良いと思う。
最後の「白樺派」の章では、武者小路実篤、志賀直哉、有島武郎、里見弴が紹介される。ここでもやはり著者の興味に応じて、取り上げ方に少し差があるように感じられる。中でも著者は有島武郎に多大な感心を持っている(同時に高く評価している)ようで、それは読んでいてひしひしと伝わってくる。結果的に僕自身も、これまであまり関心を持っていなかった有島武郎に対して興味が湧くことになった。いずれ『カインの末裔』か『或る女』は読んでみたいと思った。そういったあたり、つまり興味をかき立てることだが、それが本書の魅力に繋がるわけで、結果的に、その作家、あるいはその文学作品に対する関心が掘り起こされることになる。これこそがキーン先生の文学史を読む楽しみ(あるいはキーン作品の魅力)なのではないかと感じたりもする。